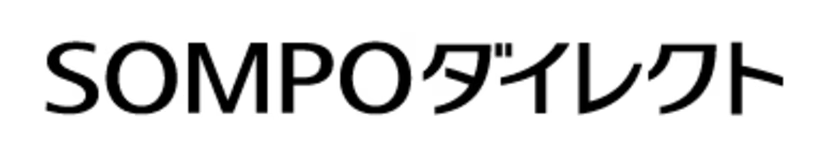最重要顧客接点であるウェブサイトのUX改善に向け、SOMPOダイレクト損害保険株式会社は「Contentsquare(コンテンツスクエア)」のデジタル体験アナリティクスを導入。
活用開始からおよそ1年、可視化されたユーザー行動データによって、どんな課題が見つかり、改善が可能になったのか?そしてインパクト分析のフル活用により、どんな効果があったのか?キーパーソンに詳しくお話を聞きました。
◆お話をうかがった方
SOMPOダイレクト損害保険株式会社
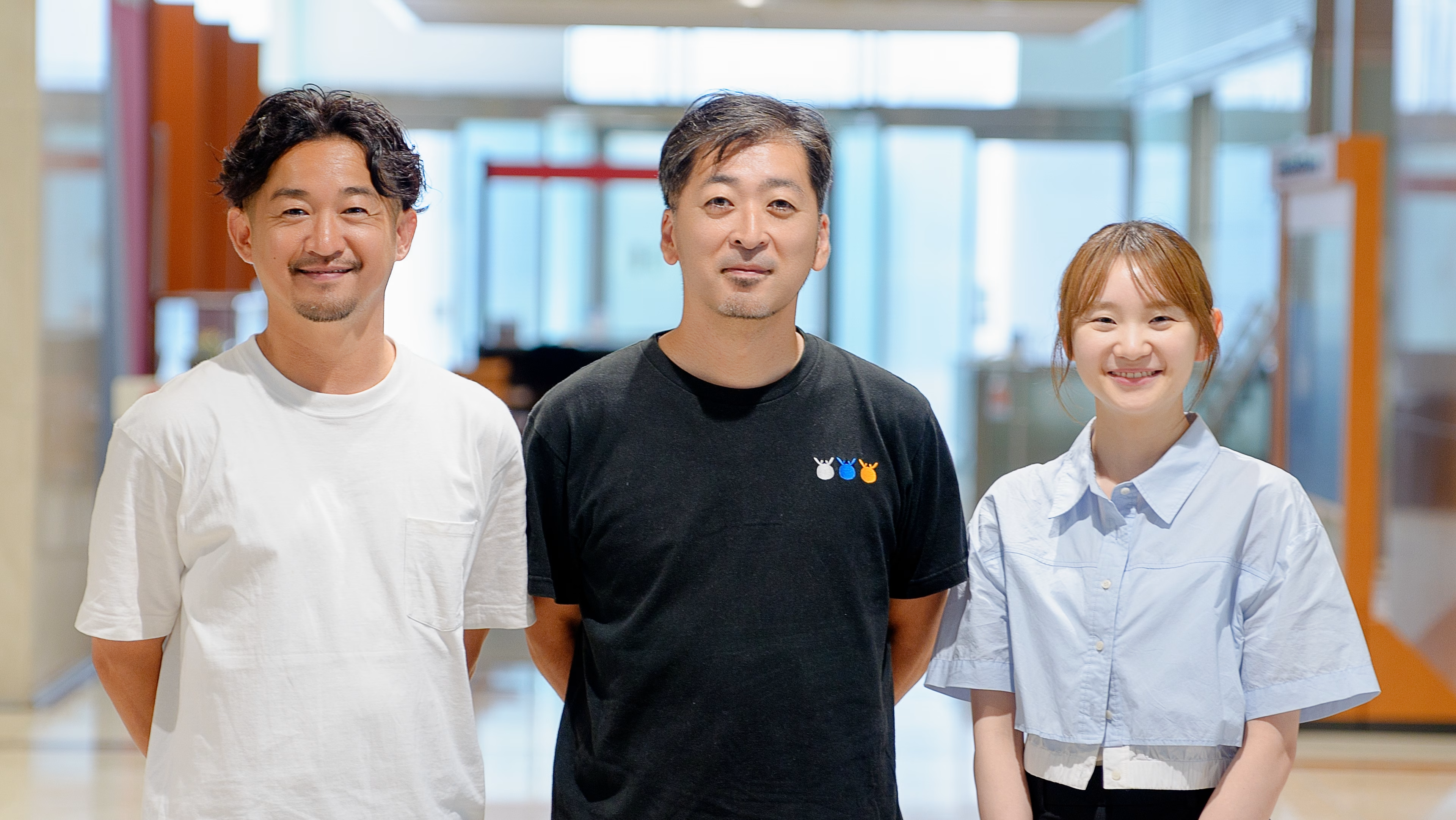
(写真向かって左から)
SOMPOダイレクト損害保険株式会社 マーケティング部
デジタルコミュニケーション 課長代理 大城 薫氏
デジタルコミュニケーション 課長 山本 俊樹氏
デジタルコミュニケーション 副長 荒井 望実氏
(※所属・肩書は2025年7月時点のもの)
SOMPOダイレクト公式ホームページ おとなの自動車保険サービスサイト
事業紹介と顧客体験(CX)向上の取り組み
── SOMPOグループにおける貴社のミッションと、顧客体験(CX)向上の取り組みについてお聞かせください。
山本氏:2024年の10月に、社名を「SOMPOダイレクト損害保険株式会社」に変更しました。主にダイレクト型の個人向け商品を取り扱っていて、「おとなの自動車保険」というブランドを中心に、インターネットを通じてサービスを展開しています。
私たちのパーパスである「デジタルで保険を体験することが当たり前の世界をつくり、お客さまの豊かな人生の実現をサポートし続ける存在」を軸に、より良いウェブ体験をお届けすることに注力しています。
金融商品である保険は、商品内容がどうしても複雑になりがちです。だからこそ、お客さまが安心して商品を選び、スムーズにご契約いただけるように、ウェブサイトの使いやすさにこだわっています。
そのために、サイト上の行動データや、コールセンターに寄せられるご意見、アンケートの結果などをていねいに集めて分析しながら、情報提供の仕方やナビゲーション、操作性といった点を日々改善し続けています。
── デジタルコミュニケーションという部署の主な役割を教えてください。
山本氏:私たちのチームでは、ウェブサイト全体のマーケティング施策の立案や結果分析を担当しています。改善内容によってはシステム部門に改修を依頼して実施しています。
こうした取り組み全体が、「お客さまに寄り添い続けるSOMPOダイレクト」という姿勢を体現するものであり、ブランド体験の向上にもつながっていると思っています。
── ウェブサイトの使いやすさで、特にこだわっている点はありますか?
山本氏:損害保険は金融商品なので、提供する私たちとお客さまの間で知識のギャップがあります。その点を自覚して、お客さまにわかりやすい用語や動線を意識しています。
また一般的なEコマースと違って、検討から契約までのカスタマージャーニーが長期化する傾向があるので、そのストレスを下げるためにも、ウェブサイトの使いやすさは重要です。自動車の損害保険は、商品としての差別化が難しいので、UI/UXの使いやすさ、わかりやすさがブランドの特色になると思いますし、ウェブサイトの読み込みのスピードなどのパフォーマンス向上や、スマートフォンでの使いやすさなども含めて改善しています。

課題と導入の決め手
──「Contentsquare」の導入前に抱えていた具体的な課題と、Contentsquareを選んでいただいたポイントや決め手、期待したことについてお話ください。
山本氏:以前は、ユーザー行動の全体像を把握することが難しく、効果的な改善策を立案したり、優先順位付けするのに苦労していました。
例えば、見積もりフォームの入力途中で離脱するユーザーが多いことがわかっていても、離脱原因を特定する定量的なデータが足りず、効果的な対策を打てずにいました。
ユーザーの行動を阻害するフリクションは至るところにあって、離脱につながっています。小さな使いづらさであっても、サイト全体で合わせるとビジネス損失が大きいことを感覚として認識できるものの、数値としては示せていない状況でした。
そこで、Contentsquareで、ユーザー行動を可視化し、データに基づいた意思決定を目指しました。Contentsquareを選んだ決め手は、その豊富な機能と直感的な操作性です。
荒井氏:導入前は、ページ間の遷移率は計測できていましたが、顧客がどこをよくクリックしているか、どの要素がよく読まれているのかなど、各ページの詳しい状況を十分に把握できていませんでした。
また、導入前も仮説に基づいた施策は行っていましたが、感覚や経験による仮説が多く、施策の優先度も属人的な判断に依存することがありました。
Contentsquareの導入を検討する上で重視した点は2点あります。
1点目は、ヒートマップや各項目のクリック率、コンバージョンに寄与した割合など、詳細な分析機能がある点です。特に、これまで可視化できていなかった「ページ間の行き来」を把握できることは大きなポイントでした。
Webアクセス解析ツールによる従来の分析は、最終的に目標の画面にたどり着いたかどうかしか分かりませんでしたが、Contentsquareによって、顧客がどのような経路をたどり、どこで阻害されているのか詳細に分析できるようになったことは非常に有益だと感じています。
2点目は、インパクト分析によって改修後の期待効果を算出できる点です。このインパクト分析は、施策の優先度決めや、システム開発を依頼する際の根拠や優先度付けとしても活用しています。

分析事例:見積り、マイページ登録画面の入力フォームを改善し、エラーや迷いをなくしていく
── Contentsquareを活用した分析を元にした施策とその成果についてお話ください。
山本氏:Contentsquareは、新規見積もり・申込み、継続申込み、契約内容変更、事故連絡の4つの顧客体験の改善で活用しています。
まず着目したのが見積もりフォームにおける離脱率の高さです。Contentsquareのフォーム分析機能で入力項目ごとの離脱率を分析した結果、特定の入力項目で離脱傾向があることが判明しました。そこで、入力項目の順番を入れ替え、必須項目を減らすなどの改善を実施しました。
また、入力途中でブラウザの戻るボタンを押すと、セッション無効となって、これまでの入力内容が消えてしまいます。
「最初から入力しなおすのは面倒、時間の無駄」と感じたユーザーは離脱してしまうので、ブラウザの戻るボタンを押さないよう、ウェブサイト上のボタンを目立たせたり、ガイドを表示しました。
大城氏:Contentsquareで、特定の手続きの画面内にあるPDFへのリンクをクリックして閲覧したユーザーのコンバージョンレートが下がるという課題を発見できました。
ユーザーが元の画面に戻れず、手続きがやり直しになっていると仮説をたてて、リンクを別ウィンドウで開くように変更した結果、リンクをクリックした方のコンバージョンレートを向上できました。
Contentsquareでは、リンクをクリックしたユーザーをセグメント化して、その後の行動を分析できるので、課題発見だけでなく、改修を実施した後の効果測定もできます。
荒井:具体的な改善事例として、マイページ登録画面の改善が挙げられます。Contentsquareのジャーニー分析を活用したところ、約半数の方がマイページ登録画面を2回以上繰り返して表示していることが判明しました。
つまり、入力にエラーがあって再度登録画面に戻っているということです。これは従来のツールでは把握できていなかった新たな発見でした。まずは、この画面でのエラー発生を抑えるための施策を実施しました。
これまでは、登録完了画面に遷移したかどうかだけを検証していました。
エラーで登録画面を繰り返し表示してから完了したのか、1回で完了したのか、という視点からの分析は、Contentsquareによって初めてできるようになりました。
また、これまでは、複数のツールを横断して分析しなければなりませんでしたが、Contentsquareは、必要な情報が一つの画面ですべて見られますし、セグメントを一つ設定すれば、異なる観点から詳細に分析ができるので、全体として分析の質とスピードがあがり、業務効率化になっています。
ABテストツールを併用していますが、分析の効率化により施策を回せる本数がアップしています。今後は、Contentsquareで確度の高い課題発見、仮説設定を行い、勝率を上げていきたいです。
分析事例:インパクト分析で期待効果を算出し、施策の優先順位付けを実施
── インパクト分析はどのように利用していますか?
大城氏:開発案件の順番を決める際、期待効果を用いて検討していますが、今まではその期待効果を示すための根拠を収集するのに時間がかかっていました。
しかも非常にふんわりとしたロジックにならざるを得ず、説得力に欠けていました。一方、Contentsquareのインパクト分析を用いた期待効果の算出は、条件やセグメントを明確に絞ることができるので、改修によって増加する保険契約数の予測といった具体的な期待効果の算出ができ、優先度決めも的確になりました。
工数がかかる開発であっても、開発部門が意図を理解してスムーズに対応するようになりました。
山本氏:インパクト分析は、計画作成においても活用しています。課題を定量的に評価して、リソースを踏まえて優先順位を決め、年度内に実施できる改善施策を設定しています。
以前は経験や知見を基に計画を立てていましたが、Contentsquareの導入により、よりデータに基づいた客観的な計画策定が可能になり、意思決定の質が向上しました。
途中で新しい課題が見つかった場合は、インパクト分析を踏まえて追加したりと、フレキシブルに計画をアップデートしながら運用できています。

他のツールとの使い分けと業務の変化
── Contentsquare以外のアクセス解析ツールのご利用状況や使い分けについて教えて下さい。
大城氏:Google アナリティクス 4 (GA4)を併用しています。ページ単体のユーザー数や流入元の確認、部門の予実管理にGA4を使っています。
一方、セグメント化したユーザーのデータは、Contentsquareで確認しています。例えば、広告経由で流入しユーザー数を確認するのはGA4を、流入してからの詳細な行動分析はContentsquareというように使い分けています。
── Contentsquareを導入して、業務はどう変わりましたか?
荒井氏:GA4を見る頻度は減り、代わりにContentsquareを確認する時間が増えました。Contentsquareでは、気になる点をセグメントごとにさまざまな観点で分析できるため、つい夢中になって時間をかけてしまいますが、その分ユーザー行動をより深く理解できるようになりました。
山本氏:Contentsquareのような視覚的なデータ活用は、部門間の連携を円滑にし、共通認識を醸成する上で非常に強力なツールとなっています。
たとえば、「この文言でユーザーが離脱している」「このデザインで操作ミスが起きている」といった具体的な課題を視覚的に共有することで、改善に向けた議論がスムーズに進みます。
ユーザーが使うウェブサイトの「現場」そのものを見せることで、自然と次の対応についての議論が始まります。開発工数が大きい改修でも、期待される効果を定量的に示せるため、社内での合意形成がしやすくなったと感じています。
展望
── 今後の取り組みや方針についてお話ください。
山本氏:今後の方針としては、「データドリブン文化の社内浸透」「SOMPOブランドの価値向上」を中心に、取り組みを進めていきたいと考えています。
1つ目のデータドリブン文化の浸透については、今後さらに重要性が増してくるテーマだと感じています。
Contentsquareの導入は、社内のデータ活用に対する意識を高めるきっかけにもなっています。Contentsquareの導入は、社内全体でデータ活用への関心と意識を高める大きなきっかけとなっています。
今後は、この成功事例を他部署にも積極的に展開し、全社的なデータドリブン文化の醸成を加速させていきたいと考えています。
特に、「ウェブサイト上のどこにフリクションがあるのか」を特定し、改善していくプロセスを共有することで、他の部門にもデータ活用の価値を感じてもらえると考えています。
マーケティング部門だけでなく、全社的にデータドリブンな意思決定が根づいていけば、より良い顧客体験のために部門をまたいだ協業もできますし、社員一人ひとりが自信を持ってチャレンジできる風土づくりにもつながると思っています。
そして2つ目が、「SOMPOブランドの価値向上」です。SOMPOというブランドが長年培ってきた信頼と安心を、デジタルの世界でもしっかりと表現していきたいと考えています。
お客さまに「SOMPOダイレクトだから安心」と思っていただけるように、ウェブサイトやアプリのデザイン、コンテンツ、サービスの一つひとつを丁寧に磨き上げていくことで、SOMPOブランドの価値をさらに高めていきたいですね。
—— ありがとうございました。